


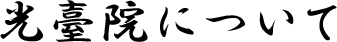
高野御室 光臺院の縁起
当院は三条天皇の第四皇子大御室性信親王が康平二年(一〇五九年)、応徳二年(一〇八五年)の二度にわたり高野山に登詣され、当地に小庵を草創し御参籠されたことに始まります。
その後、白河天皇の第四皇子覚法親王が、大治二年(一一二七年)白河、鳥羽両上皇の高野行幸に供奉して御参詣、性信親王の芳躅を慕われて御願堂、坊舎などを御建立になり、白河御所の御念持堂を移されて本堂となされました。これをもって当院の開基となります。
以来、高野御所と称され、守覚親王(後白河天皇第二皇子)、道助親王(後鳥羽天皇第二皇子)、道深親王(後高倉院第二皇子)、静覚親王等(後花園天皇御猶子)等、江戸時代中期まで二十七代に亘り各親王方が歴代の住持を務められた由緒ある門跡寺院です。又、後白河法皇、後鳥羽上皇、後嵯峨上皇、御宇多法王の列聖、高野山の行幸啓の折りには当院を宿院とされました。よって、当地を御所谷とも称されます。更に御室御所(京都仁和寺)の別院、高野御室と呼ばれ高野山内に在っても高野山の支配下に属せず、超然と尊厳を保持してきた名寺であります。なお、今日では金剛峯寺の塔頭寺院であり、また高野山真言宗の別格本山の寺格をもちます。このように皇室ゆかりの御寺であり、今日なお昔ながらの高野山の律院の面影をとどめている唯一の名刹といえます。
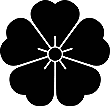

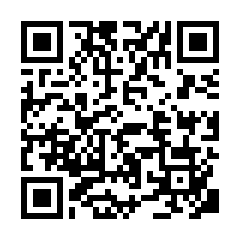
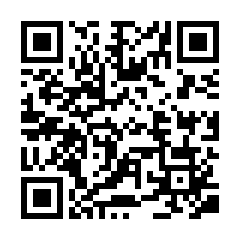
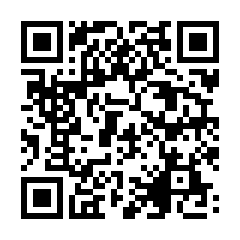
ドローン空撮による鳥の目線で光臺院の全貌を見ることができ、自由に動き回れます。目的の建物をクリックすると内部に入ることもでき、普段は解放されていないエリアも探索できます。多くの見どころポイントを設定していますので是非お持ちのスマートフォンやタブレットからご覧ください。

山門

本堂

本尊 快慶作 阿弥陀三尊立像
当院の御本尊、阿弥陀三尊立像は鎌倉時代の仏師、快慶作です。もとは後鳥羽天皇第二皇子、光臺院御室道助親王の御念持仏でありました。中央に阿弥陀如来様。両脇仏に観音菩薩様、勢至菩薩様。阿弥陀様は上品下生印、両脇仏様はわずかに膝をゆるめた来迎のお姿をされています。快慶晩年の作とされ、また快慶の最高傑作とも言われております。国の重要文化財に指定されております。

本坊・庫裏
僧侶の居住棟です。書斎、客間、茶室などがあります。

光臺院庭園
昭和を代表する作庭家、重森三玲氏作の庭園です。昭和二十八年に作庭された龍を模した光臺院庭園(龍池庭)です。

光臺院書院庭園
昭和を代表する作庭家、重森三玲氏作の庭園です。昭和三十八年に作庭された高野八葉の峰を模した書院庭園です。

道助親王御陵
後鳥羽天皇第二皇子。 建久七年十月十六日生まれ。建永元年仁和寺において出家されます。建保二年仁和寺門跡。宝治三年一月十五日、もしくは十六日に当院にて御遷化されました。光臺院御室と称され、当院裏山に御陵があります。

多宝塔
後鳥羽天皇第二皇子、道助法親王追善菩提の為に創建されました。初代(桃山時代)の塔は大阪市藤田美術館に移建されました。現在は大正五年頃、藤田男爵により再建された塔が残されております。多宝塔本尊は大日如来様(非公開)です。

関白 豊臣秀次公胴塚
文禄四年、太閤秀吉の怒りに触れ聚楽第より高野山に逃れて来られますが尚追討使を向けられ、青厳寺(現代の金剛峯寺)の柳の間にて切腹をされました。当院の裏山に胴塚が残されています。文永四年七月十五日没。享年二十八歳。

織田秀信郷 供養塔
岐阜中納言であり織田信長の嫡孫。 関ヶ原の役にて西方に属して籠城されますが、城落ちて高野山に逃れ、その後高野山麓(現在の橋本市)にて病歿されました。当院裏山の墓地に供養塔が残されています。 慶長十年五月二十七日没。享年二十六歳。

経蔵
高野山でも数少ない校蔵造りの建物で絵江戸時代の高僧 了翁によって寄進されました。鉄眼一切経が納められています

鐘楼
※拝観の受け入れはおこなっておりません。詳しくはこちらよりご確認ください。